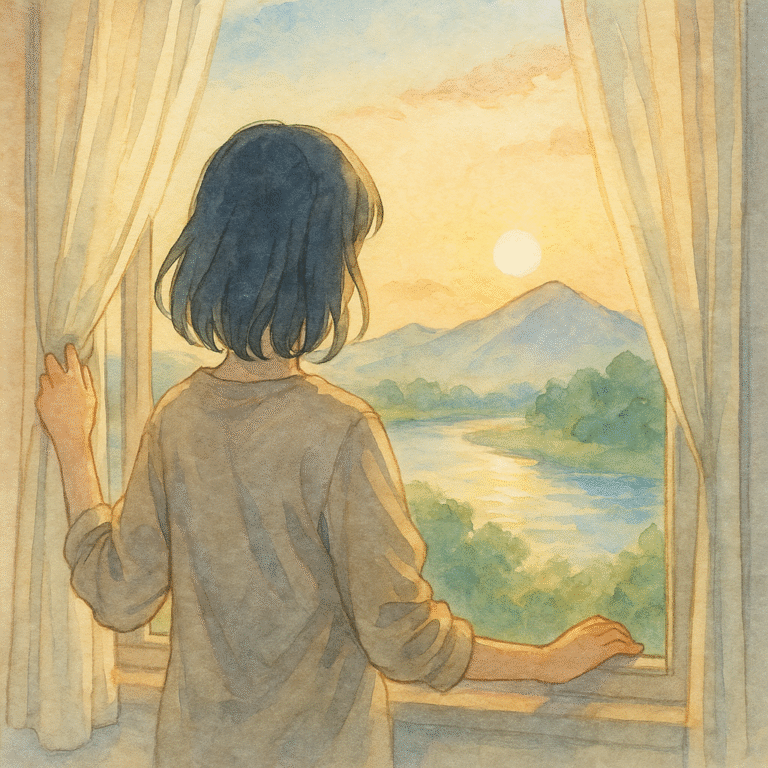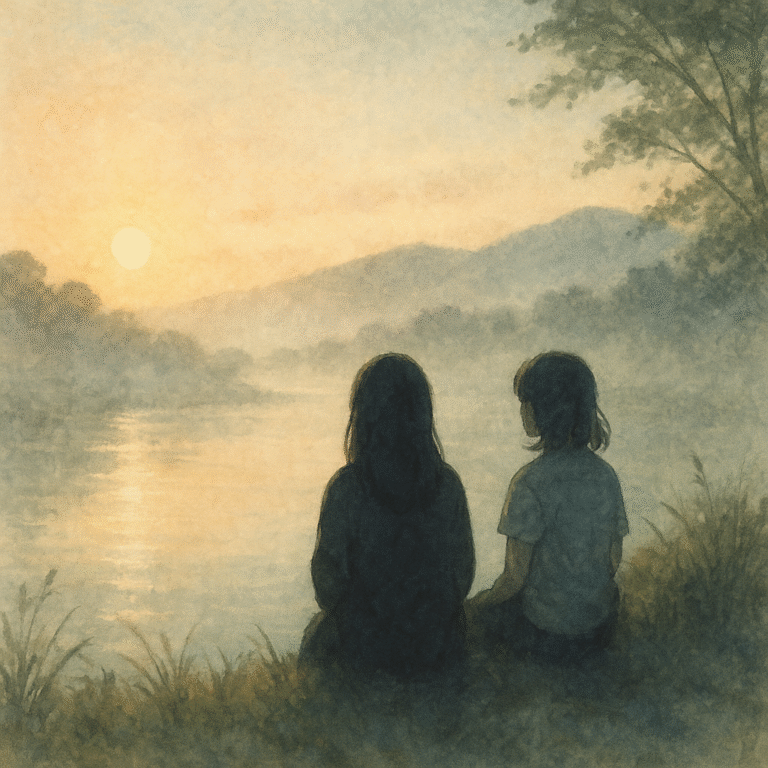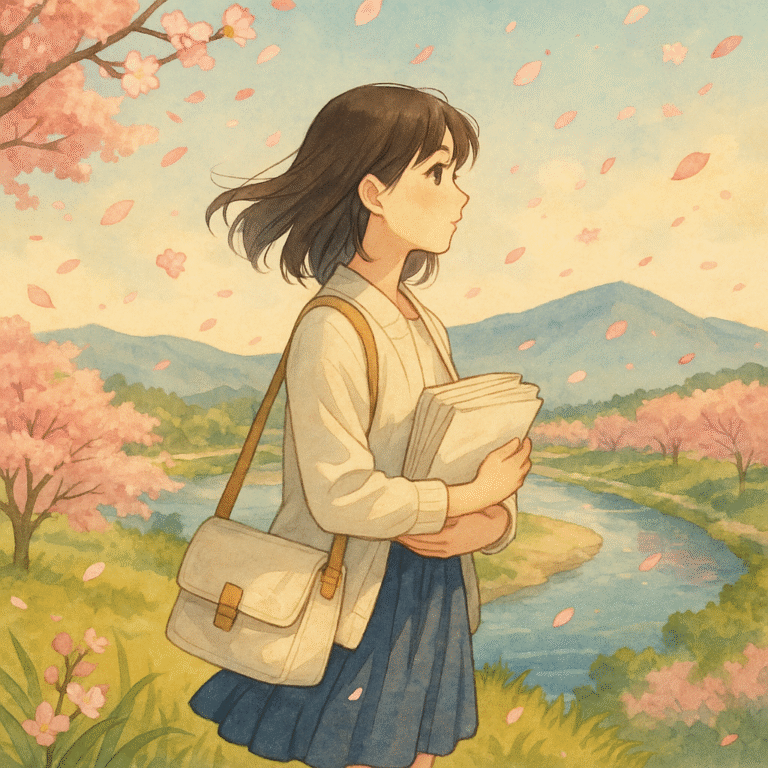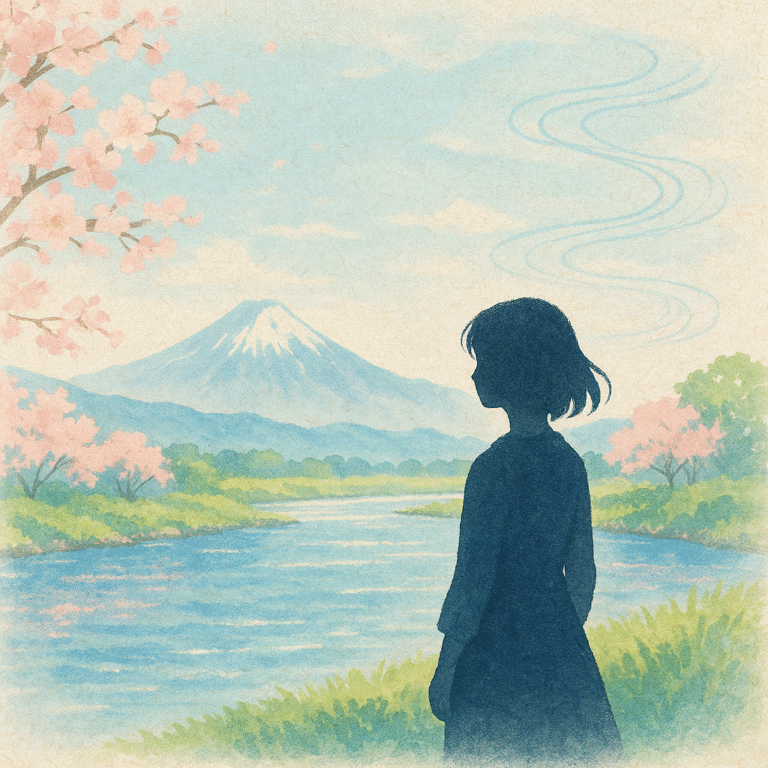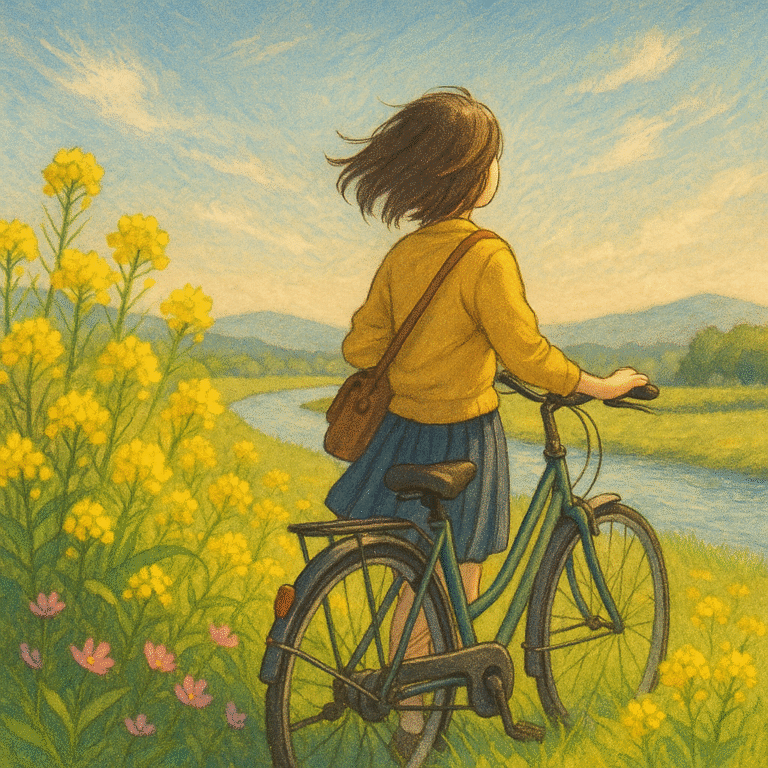1 (08) ゆるやかな季節の移ろい
5月に入り、市川三郷町は春から初夏へのゆるやかな移ろいを迎えていた。山々の緑は日に日に濃さを増し、富士川を渡る風も心地よさを深めていく。朝、窓を開けると、新緑の香りを含んだ空気が頬を撫で、みさとはその爽やかさに目を細めた。季節の巡りが肌で感じられるこの町に暮らしていることを、彼女は改めて誇らしく思った。
その日は、町の中心にある小さな公園で「みさとふれあいマーケット」が開かれる日だった。地元の農家や工房が出店し、自慢の品を持ち寄るこのイベントは、毎月の楽しみとして町の人々に親しまれている。みさとが働く「和紙工房 ゆらぎ」も、季節の便箋や限定の紙小物を並べることになっており、彼女は朝から準備に追われていた。
「みさとちゃん、こちらの商品をお願いできる?」
佐藤和子が穏やかな声で呼びかける。
「もちろんです!」
彼女は笑顔で答え、和紙の束を大切に抱えた。
マーケット会場に着くと、すでに賑わい始めていた。テントの下には採れたての野菜や果物、焼きたてのパンやジャムの甘い香り、木工細工の温もりある手触り。人々の笑い声と子どもたちのはしゃぐ声が入り混じり、初夏の空気を一層鮮やかにしていた。町の活気を目の当たりにしながら、みさとは胸の奥にじんわりと温かさが広がるのを感じた。
「おはよう、みさとちゃん!」
振り返ると幼馴染の美紀が立っていた。小学校からの親友で、今は町内の保育園に勤めている。子どもたちを連れて楽しげに歩く美紀の姿に、みさとは自然と笑顔になった。
「美紀、おはよう。今日は保育園の子どもたちと一緒?」
桜木町行きです「そうよ。みんな楽しみにしてたの。……ほら、この和紙、今年もすごく綺麗だね」
商品を手に取り、目を輝かせる美紀。その様子に、みさとは嬉しさを隠せなかった。自分が手伝ったものが、こうして人の手に渡り、喜ばれている――それが何よりの励みになった。
昼近く、ふと兄の祐介が会場に現れた。役場の仕事で運営のサポートに来ていたのだ。
「お、みさと。頑張ってるな」
「お兄ちゃん!」
祐介は出店された和紙の便箋を手に取り、しみじみと眺めた。
「和紙って、本当に温かみがあるな。お前が工房で働き始めてから、俺も和紙の良さが分かるようになったよ」
その言葉に、みさとは小さく微笑んだ。自分の歩みを家族に理解してもらえたことが、何より嬉しかった。
昼休憩の合間に、祐介と美紀と三人で、カフェの出店ブースで軽食をとった。心地よい風に吹かれながら、子どもの頃の思い出話に花が咲いた。
「昔は、こんなマーケットなかったよな」と祐介が言うと、
「そうだね。大人になってから、この町にはまだまだ知らない魅力があるって気づいたんだ」と美紀が頷いた。
「うん、私もそう思う。町のこと、もっと知りたいし、もっと伝えたい」
みさとの言葉に、二人は微笑んで頷いた。
午後のマーケットも活気に包まれ、夕方になる頃には「和紙工房 ゆらぎ」の商品はほとんど売り切れていた。片付けをしながら、和子が優しく声をかけてきた。
「今日は本当にお疲れさま。たくさんの人に和紙を手に取ってもらえて良かったわね」
「はい。町の人とたくさん話せて、ますますこの町が好きになりました」
素直な気持ちを口にすると、和子は静かに言葉を添えた。
「町を深く知れば知るほど、他の世界にも目を向けたくなるものよ。それは自然なこと。だから、焦らずにね。心の声を大切にしなさい」
その言葉が、みさとの胸に深く沁みた。町を愛する気持ちと外への憧れ。その二つが両立してもいいのだ、と初めて思えた。
夕暮れの帰り道、富士川の川面が橙色に染まり、穏やかな流れが一日の終わりを告げていた。自転車を止め、しばしその光景を見つめながら、みさとは心に小さく呟いた。
「私はきっと、この町も外の世界も、両方を知りたい」
その言葉は風に乗り、静かに町の空気に溶けていった。
――それは、やがて彼女を大きな決断へと導く小さな予兆にすぎなかった。