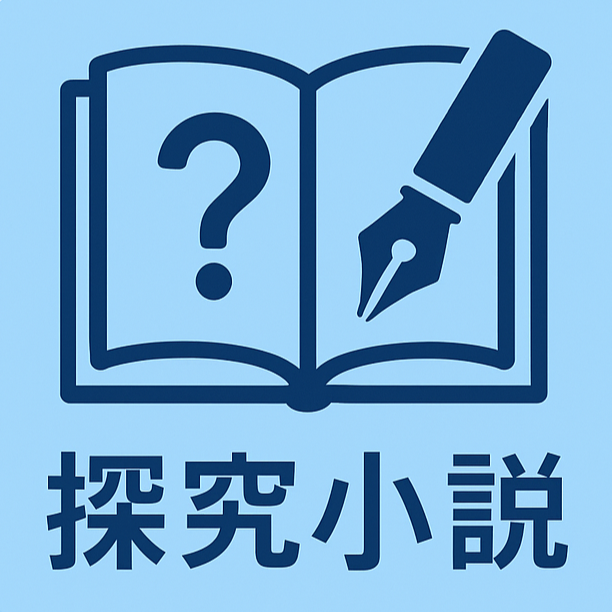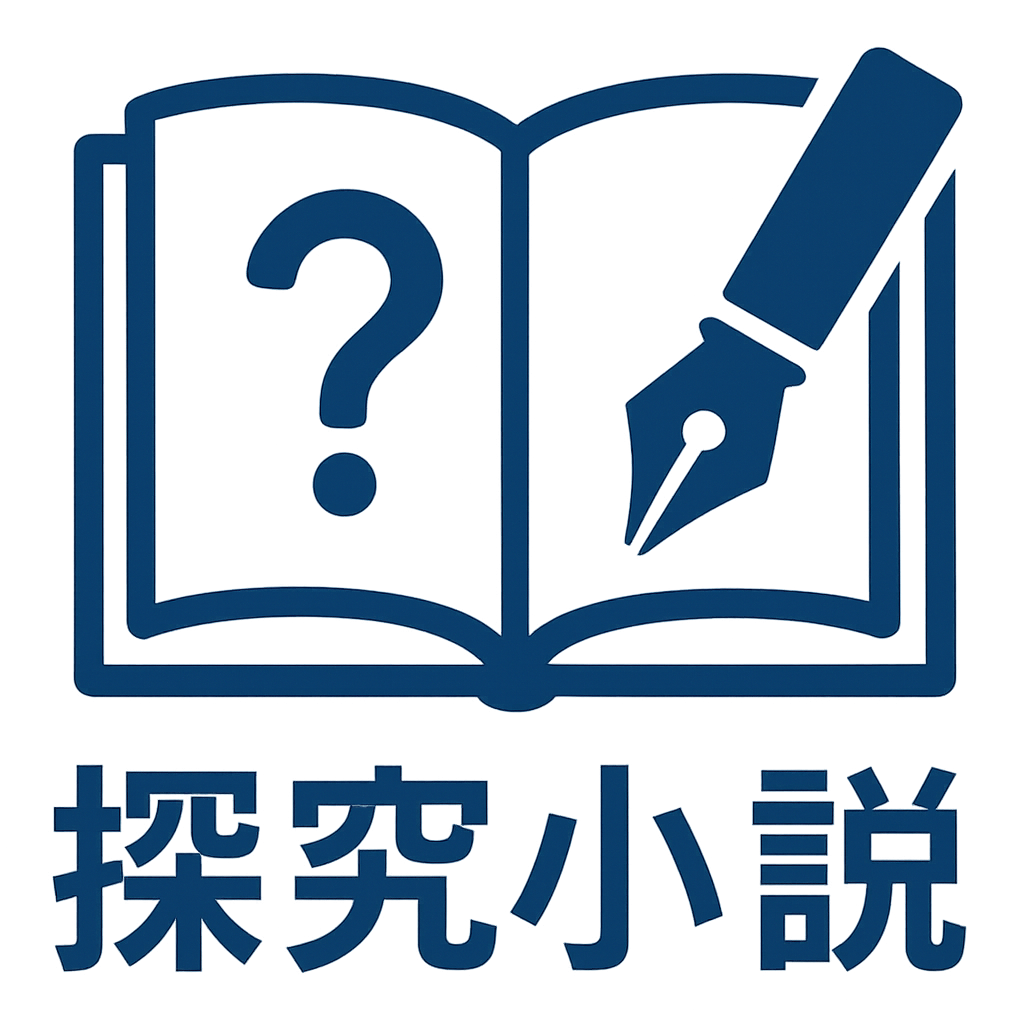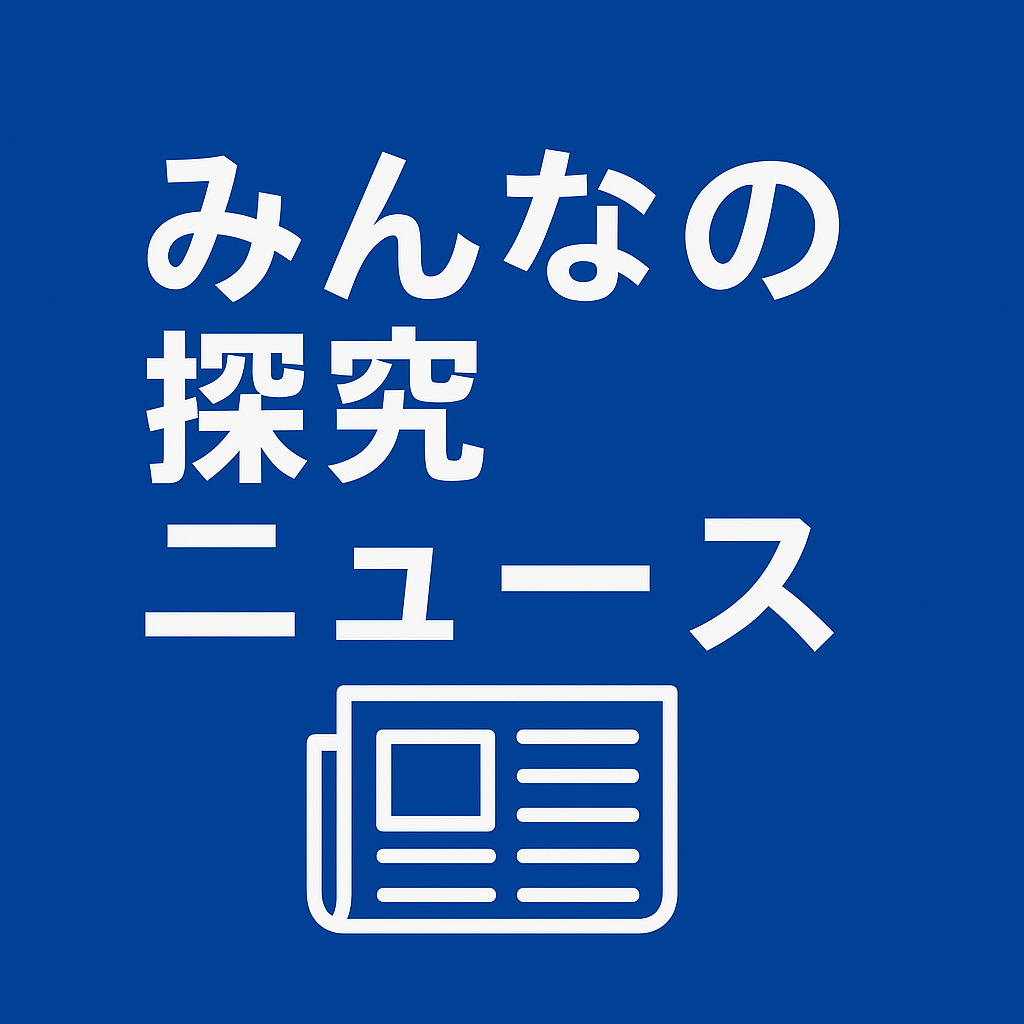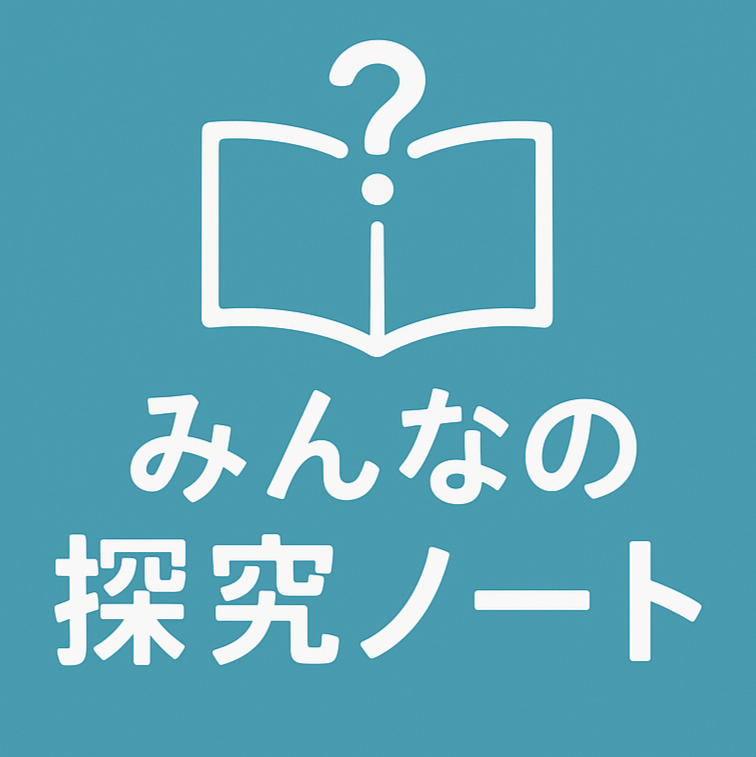1 (05) 説明会
説明会の朝、勝道は窓辺に立ち、浅い呼吸を一つ吐いた。川面は早い光を受けてまだらに輝き、昨夜から胸に居座る不安を、むしろ輪郭のはっきりしたものとして照らし出していた。
(今日は、答えを用意しに来るのではなく、問いを受け止めに行く日だ)
そう言い聞かせ、上着の内ポケットにメモを差し込む。
発電所敷地内の小さな集会所は、開場前から人の気配で満ちていた。畳は新しく、青い香りが立つ。折り畳み椅子が列をつくり、前方には白いスクリーン。プロジェクターのファンがかすかに回り始め、壁際には簡単な流域図と工事計画のパネルが並ぶ。
温泉街で旅館を営む人々、茶色く焼けた腕の農家、胸にバッジを付けた環境保護の若者たち、ヘルメットを手にした土木会社の面々。老若のざわめきの中に、互いの視線が行き交い、どの椅子にも緊張が座っていた。
時間になると、山本主任が壇上に立ち、簡潔に頭を下げた。
「本日はお越しいただきありがとうございます。新しい検討の段階で、まず皆さまの声を伺う場を持つべきだと考えました。技術の話に入る前に、私たちの姿勢として――判断の前提となる情報は、可能な限り開示します。疑問や不安を置き去りにしません」
続けて、東京帝都大学の稲葉教授が紹介される。白いシャツに濃紺のネクタイ、立ち上がる所作は落ち着いている。
「稲葉です。本日は“賛成か反対か”の色分けに向かうのではなく、前提や条件を共通化するところから始めたいと思います」
照明が落とされ、スクリーンに地層断面図が映る。教授は低く一定の調子で、地熱と天然ガスの複合発電案、地下の水理構造、既往地質データの範囲と限界、さらに今後の第三者調査の実施計画を語った
「影響の可能性は“ゼロ”ではありません。だからこそ、観測井による地下水位の常時監視、河川流量計、地盤傾斜計の設置を前提とします。データは月次ではなく、原則リアルタイムで公開します。停止基準(トリガー値)も事前に取り決め、閾値を超えた場合は工事・運用を自動停止とします」
言葉は慎重で、断言を避ける代わりに、手順と境界を明確に置いていく。勝道はメモに「可視化」「トリガー」「公開」と太字で書いた。
(“安心させる説明”ではなく、“止められる仕組み”を先に示す――)
質疑。空気がわずかに張りつめる。最初に立ったのは、温泉旅館を営む年配の男性だった。落ち着いた声だが、指先は小さく震えている。
「温泉が枯れたら終わりです。地下の熱や水をいじるというのは、目に見えないところで何をしているのか分からない。影響は“ない”のですか、“小さい”のですか」
教授は一拍置いて、ゆっくり頷く。
「“ない”と言い切ることはしません。“小さく抑えるための条件”を定義します。観測網で温泉帯の水位・温度・化学成分を併せて追跡し、変動が統計的有意に出た場合は、その原因分析が終わるまで掘削・運用を停止します。分析には第三者を必ず入れる。その費用を事前に計上します」
会場のざわめきが少し和らぐ。だが次の手がすぐに挙がる。
若い農家の女性が立つ。顎を引き、言葉を選ぶ目。
「大谷川の流量が減ったら、畑は持ちこたえられません。夏の渇水期にどうするのか、絵ではなく手当を教えてください」
勝道の胸が、反射的に強く脈打った。自分なら、今こう答える――。
教授が口を開く前に、山本主任がマイクを受け取る。
「取水量の上限は、平均流量に対して可変上限を設定します。渇水期は発電出力を下げる“出力抑制”を前提に、農業用水を優先します。予備案として、仮設の調整池と非常導水ラインの敷設計画も持ちます」
勝道は息を詰め、続きを心の中で補った。
(……そして現場は、毎朝流量を見てバルブを開け閉めする。紙の上の条件を、生活のリズムに変える役目が、自分たちに回ってくる)
環境保護団体の若者が挙手する。背筋の真っ直ぐな声。
「天然ガスの採掘で、爆発やリークのニュースを僕らは何度も見ています。ここでは“もしも”の時、誰が、何分で、どう動くのか。手順ではなく、時系列で教えてください」
教授は壇上の時計に目をやり、短く呼吸を整えた。
「警報は濃度・圧力・流量の三点で多重化、閾値の一次超過で場内退避、二次超過で地域通報。通報から三分で発電所ゲート閉鎖、五分で周辺道路規制。ガス遮断は自動弁、同時に負圧化して外部放散を抑制。地域の方の避難導線は、自治会と訓練を重ねて共有します」
若者は頷き、表情を少し緩めたが、すぐに引き締め直す。
「訓練は“いつか”ではなく“いつから”ですか」
「工事着手の三か月前から、月例で」
短い応酬が、会場の緊張を実務の温度に下げていく。
土木会社の社長が立つ。腕を組んだまま、低い声。
「地盤沈下は“起きうる”。じゃあ、起きた時の責任は? 道路や家に傾きが出たら、誰が、どこまで補償する」
山本主任が勝道の方をちらと見て、マイクを握り直す。
「変状の判定基準と補償の範囲は、事前に覚書を交わします。観測網と家屋調査の“初期値”を必ず取り、そこからの変動で補償可否を決める。費用は当社の基金で即時対応、長期化する場合は第三者委員会で協議し、継続支給の枠を設けます」
社長は小さく鼻を鳴らし、席に戻った。
(“即時”と言った。なら、現場は遅れない仕組みを作らないと――)
勝道はメモに「即時支給→現場連絡線」「家屋初期値→全戸」を書き加えた。
最後列から、細い手が上がった。赤ん坊をだく若い母親だ。
「……夜、音はしますか。揺れは。赤ん坊が起きると、私も、夫も、眠れない」
会場が静まる。大きな仕組みの話から、生活の手触りに視点が降りてくる。
勝道は咄嗟に立ち、山本から視線で合図をもらい、マイクを受け取った。
「振動と音は、僕たちが“一番”見落としてはいけないところです。振動は発電設備の基礎に制振を入れ、夜間の工事は原則しない計画にします。もし例外的に必要なときは、事前に日程をお伝えし、騒音計の数値をその場で共有します。数値が基準を超えたら、その時点で中止します」
言い切ってから、彼は手のひらの汗に気づいた。母親はうなずき、赤ん坊の背を優しく撫でた。
質問はなお続いた。宗教者の立場からの景観の問い、観光業からのブランドイメージの懸念、自治会からの避難所運営の負担配分――。言葉の往復は次第に時間の感覚を失わせたが、奇妙なことに、怒号は一度も起きなかった。代わりに、畳の上に置かれたそれぞれの暮らしが、小さく、しかし確かに揺れていることだけが、会場の底で響き続けた。
閉会前、稲葉教授は短く頭を下げた。
「本日のご意見を“合意”とは呼びません。“条件と論点の共有”の第一歩です。次回までに、今日出た項目ごとに、実施計画・停止基準・補償枠・公開方法を具体化して持参します。第三者調査の速報も合わせてお持ちします」
山本主任が続ける。
「説明は“今日で終わり”ではありません。皆さまが“納得できない”と言える場所を、続けます」
拍手はまばらで、しかしいくつかの手はしっかりと音をつくった。人々は小さなグループに分かれて、まだ話し続けている。椅子のこすれる音、名刺の交換、ため息、笑い声の手前で止まる気配。窓を開けると、川の音が戻ってきた。
壇上から降りた勝道は、外気を一口吸い込んだ。メモ帳は細かい字で埋まり、端にはいくつも矢印が飛び交っている。
(“越えるべき線”と“越えてはならない線”。今日、少しだけ輪郭が見えた)
答えではなく、境界の置き方。安心ではなく、止め方。約束ではなく、仕組み。
川面の光は午後の角度に傾き、畳の青い匂いがまだ袖口に残っている。
(技術を“人”の側に結び直す――その役目を、僕は引き受けていいのだろうか)
自問は、肯定にも否定にも行かず、ただ胸の中で静かに燃え続けた。
説明会は終わった。だが誰ひとり、完全には終われないまま帰途につく。得るものと失うもののあいだに引かれた細い線を、どうやって町の道に描き換えるのか――。
勝道は最後に会場を振り返り、深く頭を下げた。川の音が、その背中を無言のまま押し出した。