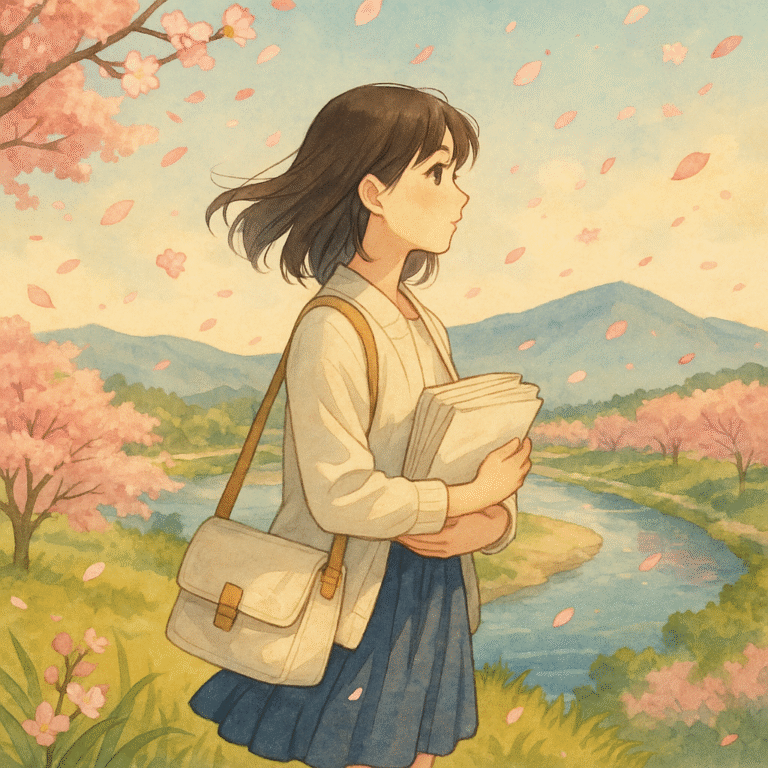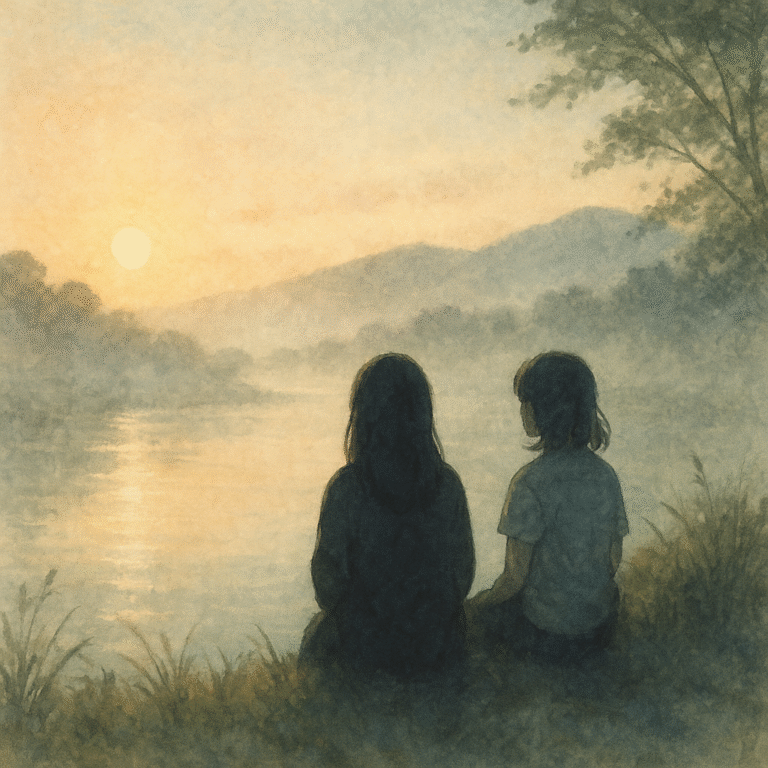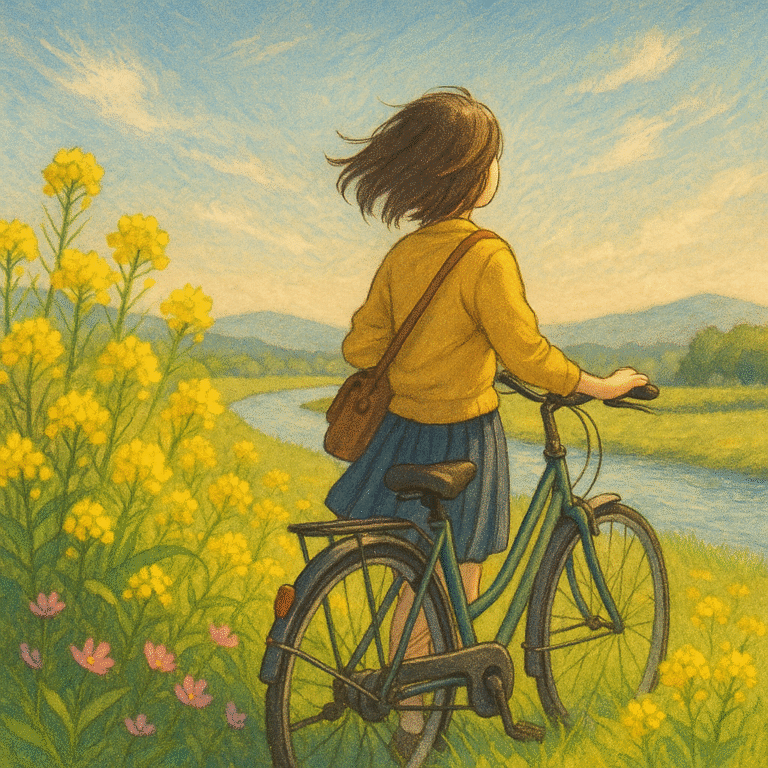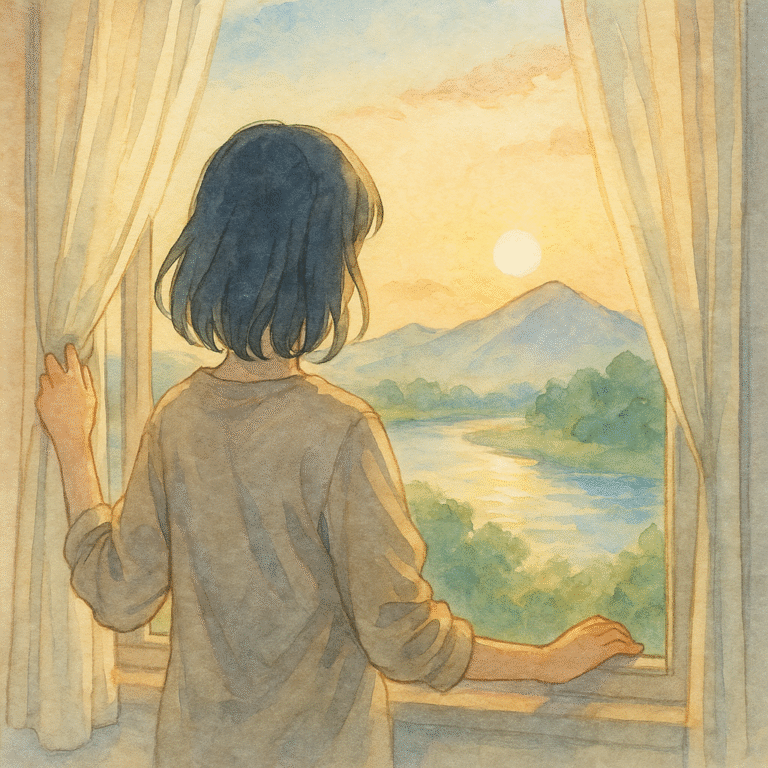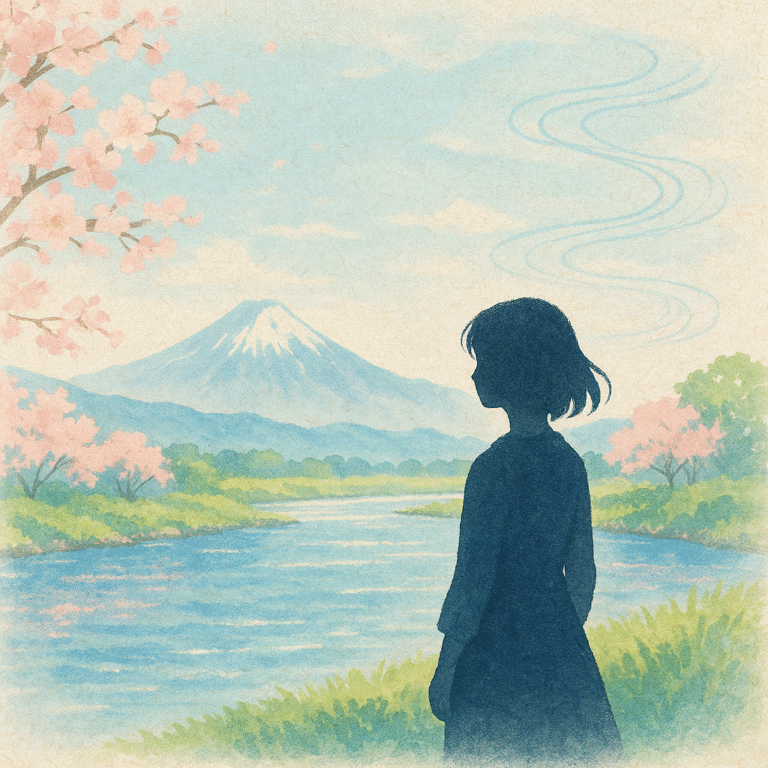1 (07) 川音が紡ぐ思い
季節はゆっくりと歩を進め、市川三郷町は新緑がまぶしい季節を迎えていた。
富士川の水面は透き通った青空を映し、風にそよぐたびに小さな波紋を広げている。岸辺の木々は鮮やかな緑を揺らし、その葉擦れの音が絶え間なく川音に重なっていた。耳を澄ませば、水の流れ、鳥のさえずり、遠くからかすかに聞こえる人々の話し声が、町の穏やかなリズムを奏でているようだった。
昼休み、みさとは「和紙工房 ゆらぎ」の裏手にある小さな庭を抜け、富士川を望む木陰のベンチに腰を下ろした。手にした弁当を広げ、一口ずつ噛みしめながら、ぼんやりと流れる川を眺める。
この数か月、昼休みになると決まってここに足が向くようになっていた。理由は自分でもはっきりしない。ただ川の音に身を委ねていると、心の奥に眠っていた何かが静かに目を覚ますような気がしていた。
「みさと、やっぱりここにいたのか」
ふいに聞き慣れた声が背後からした。振り返ると、兄の祐介が立っていた。役場で働く公務員の兄は、今日は外回りの仕事で近くを通ったらしい。
「お兄ちゃん、今日は仕事中?」
「まあな。ちょっと一息入れに来たところだよ」
祐介はそう言って、みさとの隣に腰を下ろした。二人は並んで川面を見つめる。言葉を交わさなくても、風の匂いや川音が互いの心を静かに結んでくれる。
しばらくして、兄が口を開いた。
「この町はいいよな。静かで、自然も豊かで、人も優しい」
みさとは頷いた。
「そうだね。小さい頃から、ここは安心できる場所だった」
兄は少し間を置いてから、視線を川に向けたまま言葉を続けた。
「俺も、一度は外に出てみようと思ったことがあった。でも、結局はこの町が一番だって思って残ったんだ」
「そうなんだ……」みさとは驚いたように兄を見た。
祐介は微笑み、さらに続けた。
「でもな、みさとは違う気がする。小さい頃から外に興味を持ってただろう?図書室で世界地図を広げて、国名や都市を指でなぞってた。俺はそんなお前を見て、“こいつはいつか町の外に出るんだろうな”って思ってたんだ」
その言葉に、みさとの胸が小さく震えた。忘れかけていた幼い日の自分の姿が、鮮やかに蘇る。知らない国の写真を眺め、そこに暮らす人々の生活を想像していたあの頃――。それは確かに、自分の中にあった夢だった。
「でも、私は今、この町で幸せだよ。ここが好きだから」
そう口にすると、兄は優しく頷いた。
「それでいい。でも、もし外の世界に惹かれるなら、一度ぐらい出てみるのも悪くない。外を知ってから、この町に戻ってくる。それも一つの道だ」
兄の穏やかな声は、川音に重なって心の奥に深く響いた。
みさとは、自分の中にしまい込んでいた小さな憧れが、再び息を吹き返すのを感じた。
午後、工房に戻ると、手にする和紙の一枚一枚に自然と気持ちがこもった。だが作業の合間にも、兄の言葉が繰り返し思い出される。
――この町を愛する気持ちと、外の世界を見たいという好奇心。二つの想いが、彼女の胸の中で静かに揺れ続けていた。
夕方、工房を後にしたみさとは再び富士川の岸辺に立った。夕陽が川面を黄金色に染め、流れに溶け込んでいく。彼女はその光を目に焼き付けながら、心に問いかけた。
「この町は私のすべて。でも……外の世界を見たら、私はどう感じるんだろう」
その問いの答えはまだ出ない。だが、川の流れのように絶え間なく続く時間の中で、必ず見つかる気がした。
夜、帰宅すると食卓には母の作った煮物と、新鮮な野菜の和え物が並んでいた。父が「今日も一日お疲れさん」と声をかけ、兄は穏やかに微笑んだ。家族と囲む温かな食卓は、みさとにとって何よりも大切で愛おしい時間だった。
その夜、机に向かい日記を開く。
『今日、お兄ちゃんと話して、心の中にまだ外の世界を知りたい気持ちがあると気づいた。町も家族も大好きだけど、私自身のことをもっと知りたい』
小さな文字でそう書き記すと、みさとは深く息をつき、そっとペンを置いた。窓の外では、川のせせらぎが夜風に混じって聞こえていた。
――それはまだ小さな揺らぎに過ぎなかった。だが、やがて大きな波紋となり、みさとの人生を少しずつ変えていくことになる。