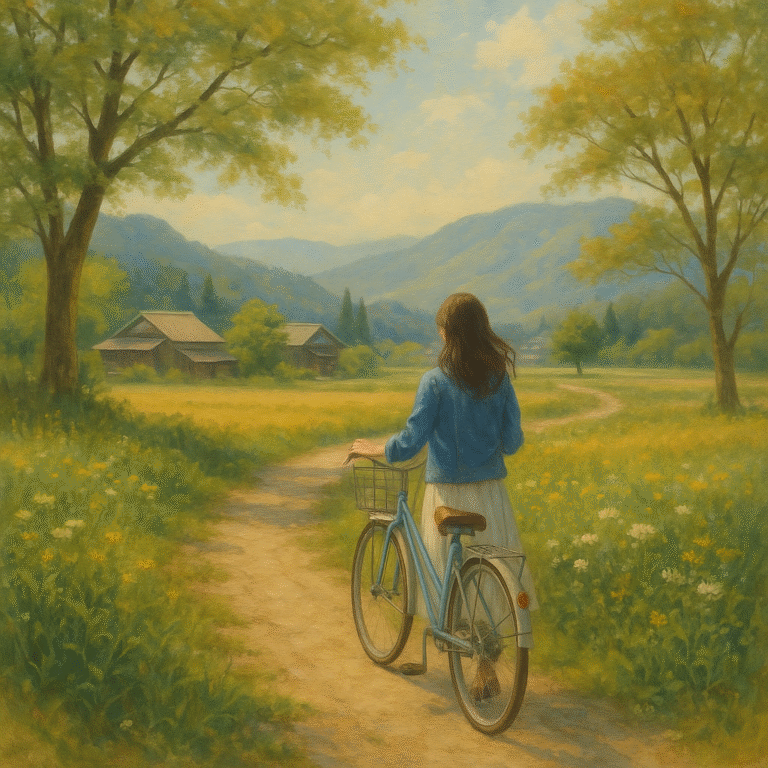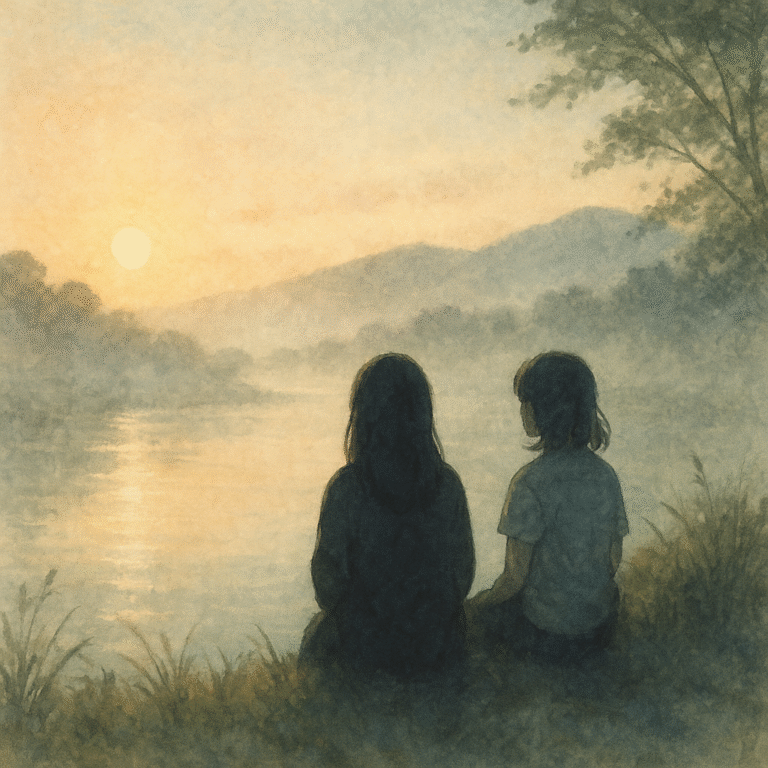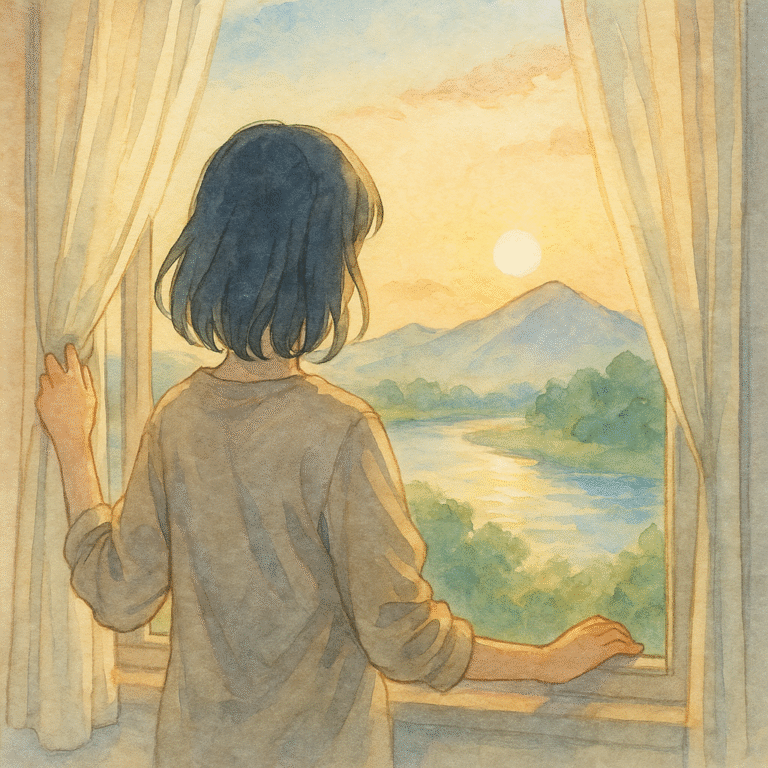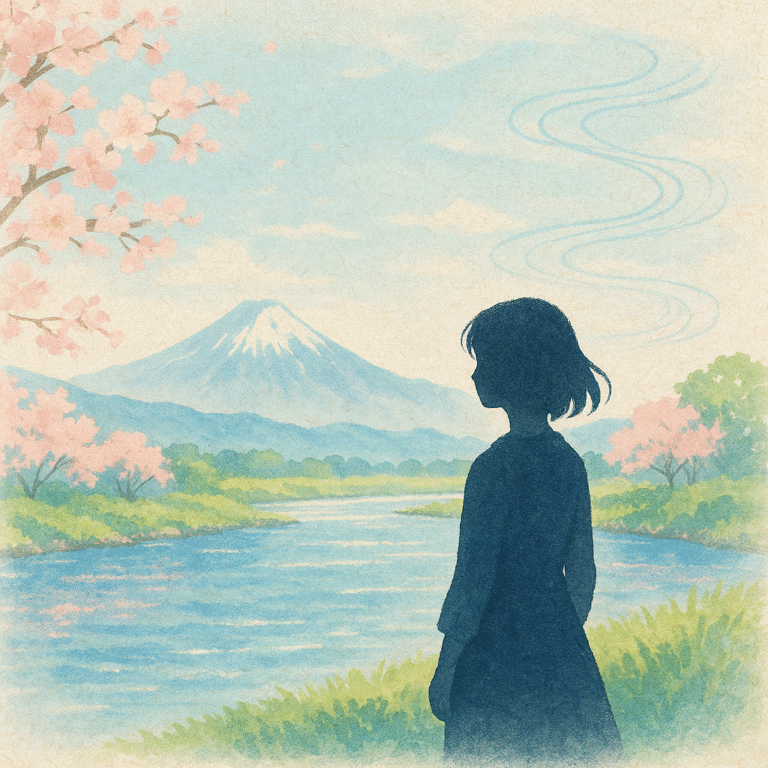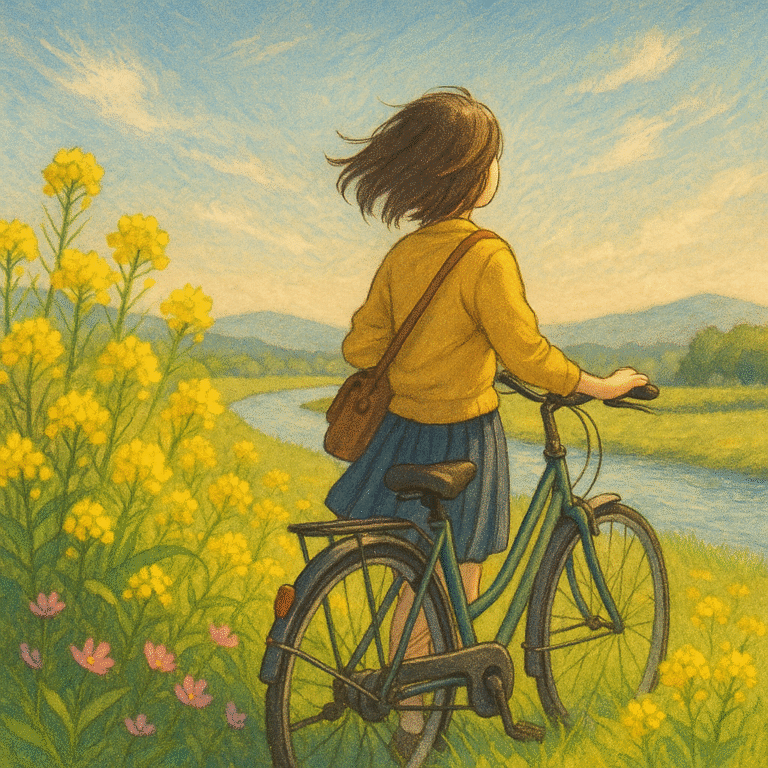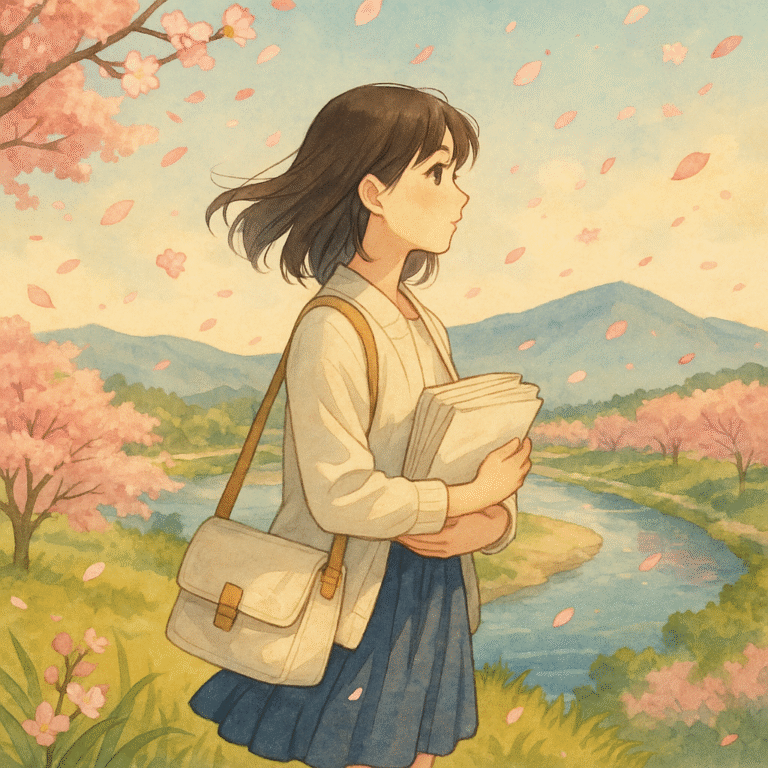1 (06) 和紙のぬくもりと家族の絆
市川三郷町の春は深まり、町は生命の息吹に満ちていた。川沿いの桜並木は散り始め、舞い散る花びらが道を淡く染めている。その中を、市川みさとは自転車で軽やかに走り抜けていた。風に乗って花びらが頬に触れ、その一瞬に春の儚さと鮮やかさが重なり合う。今日も彼女は「和紙工房 ゆらぎ」でのアルバイトに向かっていた。
工房に着くと、佐藤和子がいつもの柔らかな笑顔で迎えてくれた。
「みさとちゃん、おはよう。今日はちょっと忙しくなるわよ」
「はい、頑張ります!」
工房の空気は、和紙特有の甘く優しい香りに満ちている。紙を漉く音、乾いた紙を束ねる音、天日に干された紙が風に揺れる音――そのどれもが、みさとの心を落ち着かせてくれた。今日は地元小学校に納める特別な和紙ノートを仕上げる日で、作業場はいつも以上に張りつめた雰囲気に包まれていた。
職人たちが慣れた手つきで和紙を漉く姿を横目に見ながら、みさとは包装や検品を任されていた。一枚一枚が繊細で、同じに見えて微妙に色や手触りが違う。それらを確かめるたびに、和紙が「生きている」ように感じられた。
昼休憩になると、みさとは工房の裏手に出て小さなベンチに腰掛けた。澄んだ青空の下で母が作ってくれたお弁当を広げ、手にしたおにぎりの梅干しの酸味が口いっぱいに広がった。ふと目をやると、工房の中庭には使い込まれた道具や木枠が整然と並び、近くの物干し竿には白い和紙が風に揺れている。その光景はどこか懐かしく、彼女の胸を温かくした。
「みさとちゃん、お昼ご飯、美味しそうね」
声をかけてきたのは和子だった。
「はい。お母さんの手作りなんです。梅干しは自家製で」
「まあ、それは贅沢ね。やっぱり家族の味は特別よ」
和子は懐かしそうに目を細めた。
「私も若い頃に一度この町を離れたことがあったの。でもね、どんなに便利で華やかな街にいても、最後は戻ってきた。川の音やこの空気、そして家族のぬくもり……それが恋しくてね」
その言葉を聞いた瞬間、みさとの胸に小さな揺らぎが広がった。自分はこれからどうするのだろう。ずっと町にいるのか、それともいつか外へ出ていくのか。答えは見えなかったが、和子の静かな言葉は、彼女の心の奥に確かに響いていた。
午後の作業に戻ると、和紙の手触りを感じながら子供の頃の記憶が蘇ってきた。兄と一緒に和紙で絵本を作ったこと。母に「上手ね」と褒められ、誇らしい気持ちになったこと。あの頃の温かい時間が、まるで和紙の繊維に織り込まれているように思えた。
夕方、作業を終えて自転車を走らせていると、富士川の橋の上で足を止めた。川面には夕日が映り、赤や橙の光がゆるやかに流れていく。川はいつも変わらないが、確かに季節を映し取り、時を刻んでいた。その光景を眺めていると、自分もまたこの町と共に生きているのだと実感できた。
家に帰ると、夕食の支度をしていた母が「おかえり」と笑顔を見せ、父は新聞を脇に置いて彼女を迎えてくれた。食卓には地元の野菜をふんだんに使った料理が並び、兄は「今日は職場でこんなことがあってさ」と楽しそうに話し出した。みさとは家族の会話に耳を傾けながら、ふと幸せが胸いっぱいに広がるのを感じた。
その夜、静かな部屋で日記を開き、小さな文字で一日の出来事を書き留めた。和子の言葉、和紙の感触、家族の笑顔……その一つひとつが彼女の心を満たしていた。
「いつか、この町の素敵さをもっと多くの人に伝えたい」
書き終えたその言葉は、まだ漠然としている。けれど、確かな未来への小さな光でもあった。窓の外で静かに流れる夜風に耳を澄ませながら、みさとは深い眠りに落ちていった。
その日一日の温もりが、彼女の心に深く刻まれながら――。